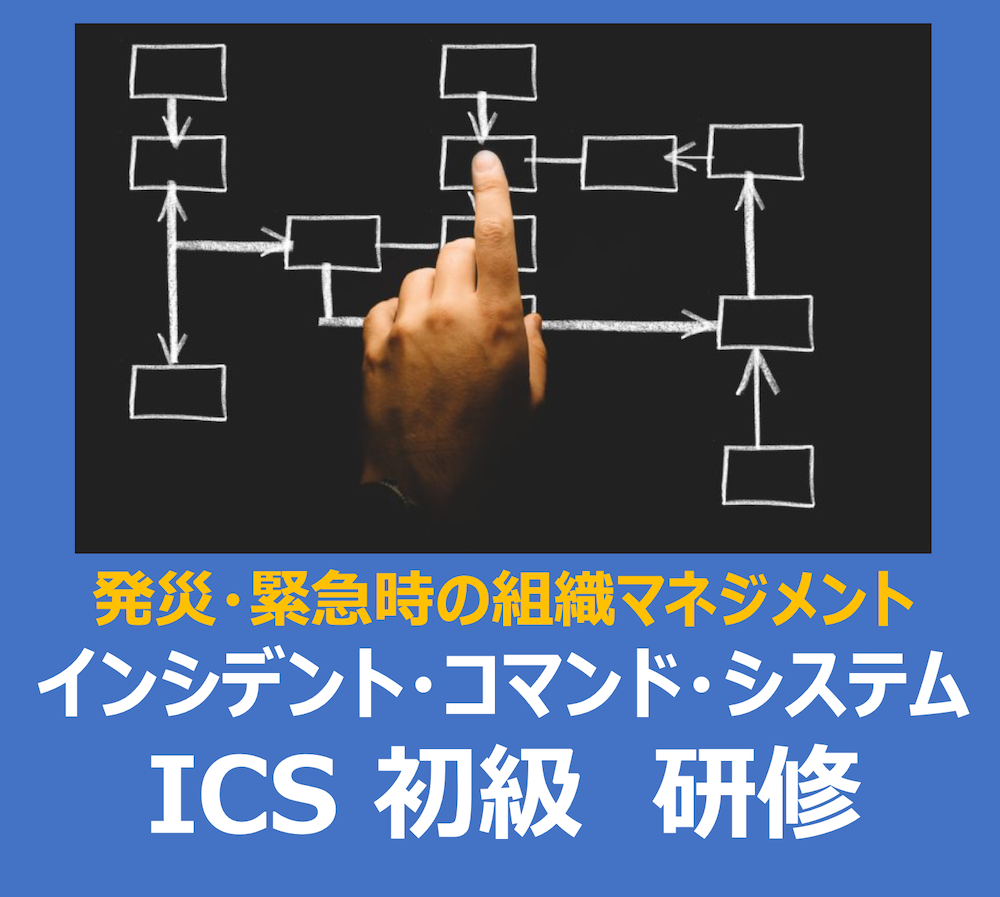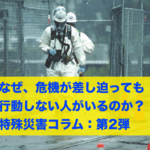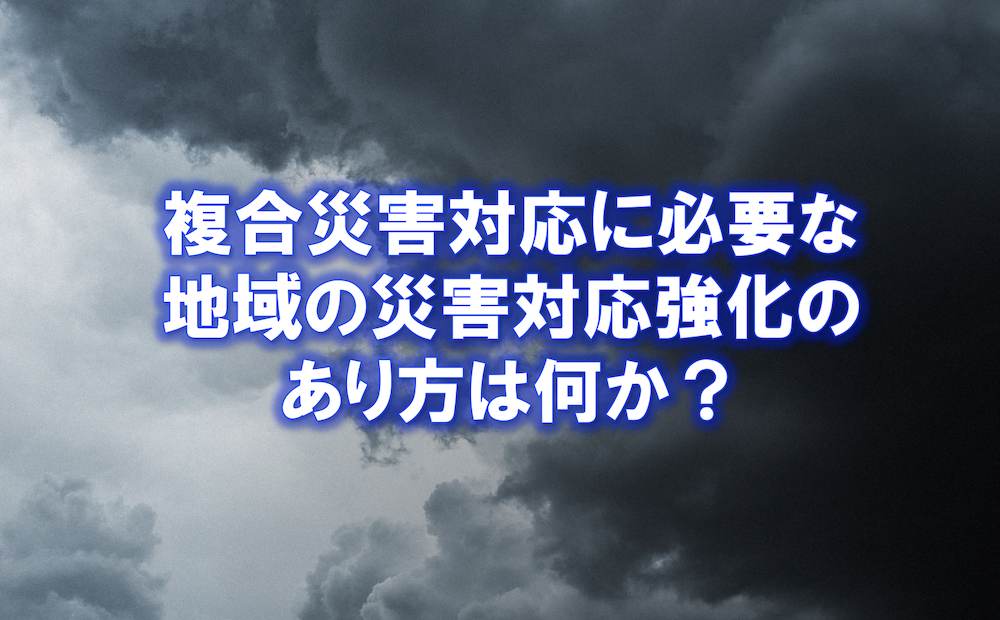
日本防災デザイン代表の志村邦彦です。
COVID-19は、世界はもとより日本でも、感染者数が再度、数的にも急増し、面的にも急拡大しています。
じわじわと増え続ける年代層の拡大も気になるところです。り患された皆さま及び関係者の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
また大雨により全国各地で被害が拡大しております。
被災された皆さまに謹んで心よりお見舞い申し上げます。
救助、救命、医療をはじめとする災害対応にあたるすべての関係者の方々のご尽力に衷心からの敬意を示したいと存じます。
今回は、複合災害だからこそ、必要な「地域の災害対応力強化のあり方」について述べてみたいと思います。
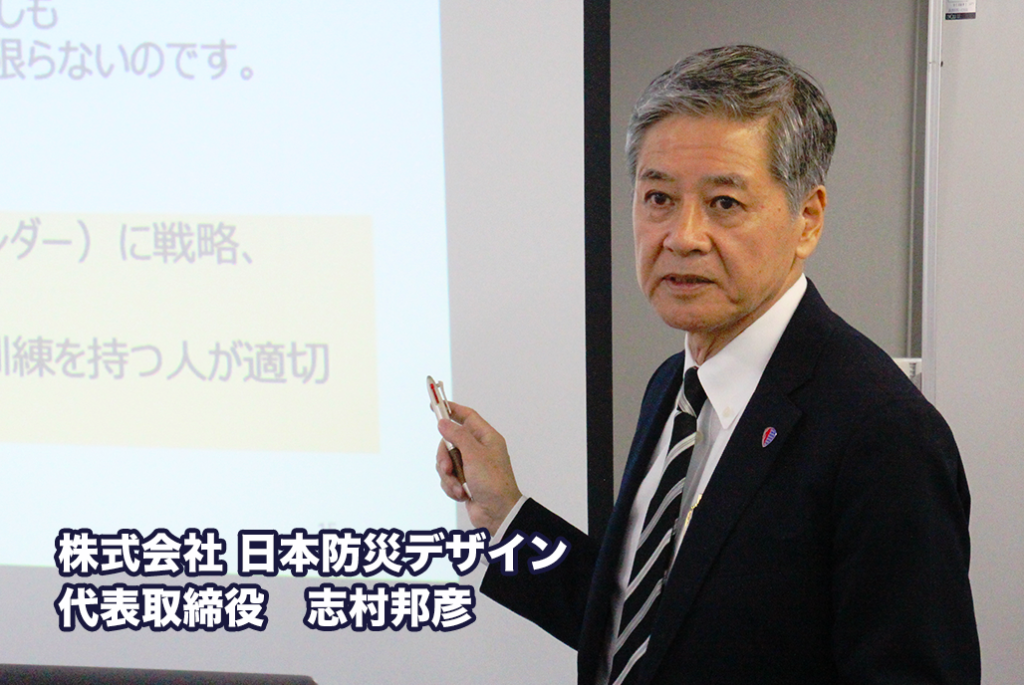
今回の複合災害で新たに見えた3つの悲劇
コロナウィルス禍の中で水害、土砂災害、地滑り災害等、複合して災害が発生しました。
悲劇その1 圧倒的な現地人手不足
現地の人の少なさ
多くの日本人が週末心を痛めたのは、甚大な被害を受けた地域の方々が口にする現地応援人材の少なさであったはずです。
行けない辛さと待つ辛さ
応援に駆け付けたい人でも、COVID-19であるがゆえに、現地に入れないもどかしさを感じながらも、どんどん悪くなる状況を見ているしかない悲劇と、それでも応援に来てくれることを期待するしかない人たちの悲劇が、全国で起きていることは想像に難くありません。
悲劇その2 災害特性に対する公助の限界
よく言われる公助の限界
公設消防、警察、自治体等いわゆる「公助」にも悲劇は起きています。ニュースなどで盛んに取り上げられている公助の限界としては、医療機関の医師、看護師の不足、病床数の限界、保健所等の業務処理量の限界等が言われています。
線状降水帯という厄介者
ところが今回の複合災害の、最大の課題は、一義的には「線状降水帯」という災害の特質がこれだけの死者・行方不明者・負傷者を出した背景にあります。通常の「台風」であれば、発生覚知から上陸までを予想し、発災前のタイムラインを作成し、何日も前から襲来時を(ゼロアワー)として、時間を遡り、それまでに、消防、警察、行政、自衛隊を含めて、何をいつまでにやるかが決められます。また、発災以降も時間とともに何をやるかがおおよそ決められます。
できないことが多いまま被災者が増える悲劇
ところが、「線状降水帯」の発生場所の特定の難しさと、災害発生までの時間の短さを考えると、タイムラインの3日分を数時間に圧縮するわけですので、公的機関がやることは多岐にわたると思われます。例えば全市民の避難誘導に職員を貼りつけることは、実際には不可能ですし、火災における「予測活動限界時間」のような概念を水害にあてはめれば、「職員もこの状況になったら、活動をやめて命のために現場退避すべき」となれば、現場でできることは本当に限られてしまって、できなかったがゆえに災害に巻き込まれる市民等が発生する悲劇を目の当たりにするのです。
悲劇その3 何をやるかわからなけどとりあえず行く
セルフディスパッチ禁止
現場第一線の公的機関にしろ、ボランティア組織にしろ、資源(ヒト、モノ)は適切な量と質を求めています。資源量が多すぎると、現場はその扱いに困りますので、米国のインシデント・コマンド・システムでは、セルフディスパッチ(自分で勝手に配置につく、勝手に現場に行くこと。勝手に現場に物資をおくること)を固く禁じています。資源はあくまでも現場の要求にそって行われるべきです。3.11の際に、各地からのプッシュ型支援物資で、必要のないものが届いた市町村は大いに困り、逆に必要なものがいつまでもとどかない市町村も大いに困りました。受けるほうの悲劇を考えて送りたいものです。
とりあえず行くことによる悲劇
今回も一部でCOVID-19感染者が被災現場に入ったとの情報があります。無防備で現地に入ることは特に慎むべきです。通常チェックインの際には、必ず個人用防護具関係の注意がなされます。
水害、浸水地が乾燥してくると、ほこりが舞いますが、その中には、COVID-19や他のウィルス、古い建物から出たアスベスト、大腸菌、破傷風等の細菌などが含まれていると言われてます。有害物資の流失も考えられます。ヘルメットとマスクもつけずハチマキだけで取り組む支援は、更なる悲劇を起こす可能性があります。
公助と自助・共助の間に誰が立つのか
現地の人手不足、公助のできることの限界、地元の状況を分かり危険を回避できる集団がいて、地元で主体的に活動できる組織となれば、、米国の消防システムのお手本にもなった消防団があります。
日本唯一のオールハザード組織:消防団
「消防団」という名称の火災関係の組織ですが、実態はTV画像でもよく見る通り、地震でも、津波でも、大雨でも、台風でも、土砂災害、地滑りでも、その姿が出てきます。ある意味「オールハザード」なのかもしれません。
しかしながら、消防団の実態としたら、「火消し訓練」が中心となっています。
地元で危機対応に問題意識ややる気をもつ若者に世界標準の教育を授け、その機能と効率性を高めてはいかがでしょうか。
今後、地域における甚大災害に限られた人数で対応せざるを得ないとすれば、また、市区町村の首長に判断を仰ぐプロセスに限界があるとすれば、地区密着の消防団に、インシデント・コマンド・システムのようなオールハザードの危機対応組織の作り方や、コミュニティ・レスポンス・プログラムのような世界で実証されてきた「共助の基本」を教えることで、地域防災力、地域レジリエンスの強化に、十分結びつくと考えます。
弊社は、市区町村さまで、ご希望があれば、モデルプランを試行する用意はありますので、ご関心があればお声がけください。(消防法の中でも対応可能です)
了
【関連情報】日本一わかりやすいICSのコラム一覧
【第1回】インシデントコマンドシステムの概要・インシデントとは何か?
【第4回】インシデントが起きたら初めにやること①:まずは指揮者(Incident Commander)を決めよ
【第5回】インシデントが起きたら初めにやること②:被害状況を把握せよ
【第6回】インシデントが起きたら初めにやること③:「何はともあれ人命優先」が危機対応の最大原則
【第7回】インシデントが起きたら初めにやること④:メンバーのチェックイン、チェックアウト
【第14回】インシデント・コマンド・システムにおける目標設定
【第15回】計画(IAP:インシデントアクションプラン)を立てる
【第16回】事態対処部門(Operations Section)の役割・組織編成のやり方
【関連情報】ICSのセミナー情報
当社でも、今後のオールハザード(すべての災害)に対応する
インシデント・コマンド・システムに関するセミナーを実施しております。
情報はこちらをご覧ください。
【開催日】
2020年8月26日(水)10:00~16:00
詳細はこちら↓ ↓ ↓
https://jerd.co.jp/academy/ics20200709/