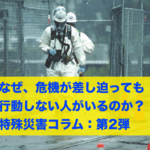今回は、ICS(インシデントコマンドシステム)における目標設定についてお話しいたします。
第5回のコラムにて、「被害状況を把握する」ことについて説明しましたよね。(まだ読まれていない方は、【第5回:日本一わかりやすいICS講座】インシデントが起きたら初めにやること➁:被害状況を把握せよをお読みください。)
被害状況を確認するのは、「目標設定」のためでもあるのです。ICSでは、通常の組織運営、会社経営と同じように、インシデントが収束するまでの目標を明確に立てることが重要です。
今回は、その目標設定について詳しくお伝えいたします。
目標設定の前に・・・目標・戦略・戦術の違いについて
会社の中でも「目標・戦略・戦術」について議論することってありますよね?
これを明確に切り分けるってとても大事なんですよね。何故ならば、どのような目標を立てるかによって、その後にある全てのプロセスに影響を与えることになりますからね。もし今までスルーされてきたならば、これを機にしっかりとおさえておきたいところです。
- 目標:組織の目指すべき方向性。場合によっては数値で示されることもある。
- 戦略:目標を達成するために、組織の中にある資源(人・モノ・お金・情報など)を、どこにどれだけ配分するか決めること。
- 戦術:具体的な取り組むべきことを決めること。
さて、この3つの中でもっとも大事なのはどれでしょうか?
もうお分かりかと思いますが、「目標」がいちばん大事です。何故ならば、どんな目標を立てるかによって、戦略・戦術がガラッと変わってきますからね。目標→戦略→戦術の順に立てていくのが大原則です。ICSでも、この順番を間違えると痛い目をみます。
余談になりますが、戦術をさらに細かいタスクに細分化して、いつまでに・誰が・何をやるかを決めることを「計画」と言います。計画については、次のコラムで詳しく扱ってまいります。
ICSにおける目標設定の意義
ここまではICSに限らず目標の一般論についてのお話になります。ここからは、ICSにおける目標設定の意義についてお話していきます。目標設定が必要な理由は、大きく2つあります。
- メンバー全員の意識合わせのため
- 変化する現状とのギャップを常に意識するため
①メンバー全員の意識合わせのため
ICS(インシデントコマンドシステム)を勉強していくと段々とわかってくることなのですが、ICSって詰まるところは災害対応のための「実践的な組織づくり」に他なりません。災害の現場指揮を担う指揮者のもと、そこに集まったメンバーが一つの組織として、災害の収束に向けて動きます。
みなさんが、もしどこかの組織に属しているならば、その組織の目的・目標って必ずありますよね? 会社の場合なら、いくら社長一人が「今年は売上目標〇〇〇億円を目指すぞ」と意気込んだからといって、社員がそれを知らなければ、目標達成などありえません。
ICSでも同じです。「災害の収束」という一つの目的に向けて、具体的な目標を立てて、組織に所属するメンバーと共通認識をもちます。メンバーの考えていることがバラバラの中で、効率的な事態の収束など見込めないのです。
でも、明確な目標があれば、メンバーもその目標に向かって自主的に判断し、主体的に行動できるようになります。そのことにより、現場指揮官の負担が減ることにもなります。
メンバー全員との意識合わせの仕方については、ブリーフィングの場を設ける必要があります。それに関しては、追って共有していきたいと思います。
②変化する現状とのギャップを常に意識するため(差異分析のため)
目標設定をする上で前提として抑えておきたいことがあります。それは、被害状況も目標も、時々刻々と変わるということです。
たとえば、大震災の場面を想像してください。ある時点で、Aエリアに被災者が100人いるという知らせがあって、その100人を救助に向かいます。ところが、実際にAエリアに駆けつけてみたら、被災者は150人に増えていました。
そうなると、対応方法は変わってきますよね。もし被災者が100人だけならば、救助隊を20人派遣すればよかったかもしれません。しかし、150人とわかった時点で、派遣する人員を増やさなければならないかもしれませんね。
前の章でも申し上げたことですが、(特に大震災のような規模の大きなインシデントの場合)被害状況は時間とともにガラッと変わります。そして、変わったとしても、いつに比べて・どれくらい変わったのかを把握しておかなければなりません。
そういう意味で、常に前との差異がどうであったかを確認しておかなければならないのです。
目標の立て方
目標を立てる意義は、災害対応に関係する人たちが、共通認識を持つことにあります。曖昧な目標では誤解も生じかねません。目標の立て方としては、「SMART」のフレームに基づいて立てていくと良いですね。
何を(What)達成すべきかを明確にし、どのように(How)達成すべきかは現場指揮者の判断に委ねるところがポイントです。
- S(Specific):具体的である
- M(Measurable):測定可能である
- A(Action Oriented):実行可能である
- R(Realistic):現実的である
- T(Time Sensitive):いつまでにやるかが明確である
文責: 志村邦彦
ご質問・お問合せ:shimura©jerd.co.jp (©を@マークに変えて送信ください)
日本一わかりやすいインシデント・コマンド・システムのコラム一覧
【第1回】インシデントコマンドシステムの概要・インシデントとは何か?
【第4回】インシデントが起きたら初めにやること①:まずは指揮者(Incident Commander)を決めよ
【第5回】インシデントが起きたら初めにやること②:被害状況を把握せよ
【第6回】インシデントが起きたら初めにやること③:「何はともあれ人命優先」が危機対応の最大原則
【第7回】インシデントが起きたら初めにやること④:メンバーのチェックイン、チェックアウト
【第14回】インシデント・コマンド・システムにおける目標設定
【第15回】計画(IAP:インシデントアクションプラン)を立てる
【第16回】事態対処部門(Operations Section)の役割・組織編成のやり方
インシデント・コマンド・システムのセミナー情報
インシデント・コマンド・システムに関するセミナー情報はこちらをご覧ください。