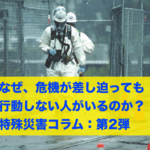ICS(インシデントコマンドシステム)では、現場指揮者(インシデントコマンダー)の指揮のもと災害対応にあたります。とはいうものの、災害の規模が大きくなれば、現場第一線の方々の努力だけでは、対処できないことになります。
そこで、現場第一線で活動する要員を後方から支援する災害対策本部が大事な役割を果たします。
映画「シンゴジラ」をご覧になった方ならばイメージができると思いますが、あのような形で災害対策本部が立ち上がります。あんなに多くの人たちが収容できていくつもの画面が表示されるような素晴らしい部屋でなくてもいいのですが、何らかの情報を集約して、共有して、大きな方針を立てる場所が必要となってきます。
大きな災害があると、「災害対策本部」と同じような名称をもつ組織は、いろいろなところに登場するわけです。
- 災害対策本部ってなに?
- 災害対策本部の機能はなに?
- 災害対策本部って何をするところなの?
というようなことについて、ご説明したいと思います。
実は、この災害対策本部の運営が、災害対応の成否に、ほんとうに大きな意味を持ちます。
勝負を決める災害対策本部?
甚大災害は、その被災地域にあるどんな企業や組織にも平等に襲いかかります。
その中で、少しでも被害金額を少なくし、復旧時間を短くし、操業を早く回復し、必要な製品やサービスをいち早くお届けできれば、お客さまの信頼を強固なものにでできるし、なによりもエンドユーザーである日本国民のためになることは論を俟ちません。結果として、社会的な評価であるブランド力が高まるかもしれません。その勝敗は、この災害対策本部運営の良し悪しにかかわるといっても過言でありません。
だって、「甚大災害の対応と事業継続」ということは、「経営環境の変化にどう対応するか」という、企業経営の「ど真ん中のテーマ」じゃないですか。いつもお取引いただいている永年のお客さまが、ほんとうにお困りになっているときに、自社は何をするかという話ですものね。
だから、企業戦略的にみれば、甚大災害への対応いかんにより、マーケットシェアやブランド地位を揺らがし、平時には考えられないほどの圧倒的な差が生じる機会であるともいえます。
難しそうな話になってきましたが、ご安心ください。成功させるためには「3つの機能」と「3つの道具立て」のことだけを覚えていただければ、大丈夫なので。
前置きが長く成りましたが、お話をすすめましょう。
いつも英語が出てきて恐縮ですが、ICSでは、災害対策本部を、EOC (Emergency Operation Center)と呼んでいます。これからもEOCという言葉が出てきたら、この災害対策本部だと思ってくださいね。
災害対策本部(EOC)の3つの機能
災害対策本部の大きな機能としては、大きく分けて次の3つがあります。
- 直面するインシデントにかかわる様々な情報の収集→集約
- 情報の意味づけ(インテリジェンス化)→優先順位付け→目標・計画の策定
- 情報の配信→周知徹底→発表(含む広報活動)
イメージとすれば、災害対策本部(EOC)が全体の頭脳で、そこから目、耳、鼻、舌、皮膚、手先、足先までに、「神経系統を張り巡らせ」て、多くの部分が緊密な相互連関をもちながら、体全体が統一的かつ合理的な動きを、EOCが司る感じです。
インシデントを、目で見て、耳で聞いて、風向きなどを肌で感じて情報を収集します(機能1)。その情報から起きていることの内容を解釈し、何をすべきかを考え、方向性を決めます(機能2)。決めたことをそれぞれの体の部分に伝え、全体を円滑に動かします(機能3)。そんなイメージです。
災害対策本部(EOC)の機能1:情報の収集・集約
災害対策本部(EOC)は、インシデントの状況、地形、気象、海象、対応部隊の組織体制、配置、有害物質の有無、影響範囲、使用可能なリソース(人的、物的)等の情報を集約し、災害対応にあたる人々に広く提供します。
通常は「状況共有画面(COP: Common Operational Picture)というシステム画像をイメージしますが、そんなシステムがなければ、会議室の黒板やホワイトボードに書き込んでも構いません。要は、災害対応者間で現状がどうであるかを共有します。(COPについては、別に説明します)
災害対策本部(EOC)の機能2:情報の意味付け、目標・計画の策定
災害対策本部(EOC)では、収集した情報を分析して、意味付け(インテリジェンス化※)し、やるべきことの優先順位を検討し、全体目標および当面の対応計画を策定します。
※インテリジェンス:意思決定に資するよう情報を評価、分析したもの。予想、想定を含む。
災害対策本部(EOC)の機能3:情報の発信
災害対策本部(EOC)からの情報発信には、二つの意味があります。
一つは、EOCで決められたことを、内容別に関係する各部門、チーム、ディビジョン、ブランチ、ユニット等の組織ごとに、瞬時に、かつ確実に配信し、手待ち時間や資材などの誤配送などのプロセス支障を極力削減することを目指します。
もう一つは、インシデントブリーフィングなどの組織内の情報周知とその徹底による安全性と効率性の確保をはかるとともに、プレス対応等の広報活動も含む情報の発信です。
成功する災害対策本部(EOC)の道具立て
災害対策本部(EOC)の機能って、情報の収集、情報の意味付け、情報の発信って、「情報」ばかりが並んだけど、なんだかややこしくてわかりづらい、とか、EOCが大切なことは、わかったけどじゃあどうすればいいの? というご意見があっても当然です。それについてわかりやすく説明していきますね。
災害対策本部(EOC)を機能させるには次の3つの道具をご用意いただければ、勝てます!
- 道具1. 状況共有画面(COP: Common Operational Picture)の提供および情報受信・配信ができる統合リスクマネジメントシステムの導入
- 道具2. 標準行動指針の策定・導入
- 道具3. 本部運営者向け訓練
本当にこの3つだけです。とは言うものの、それがまた難しいと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
「いやいやいや、うちの会社には、そんな設備もないし、お金もないし、ましてや、上司が防災に金を出す気もないので、、、、」
そんな言葉が聞こえてきますよ。
でも、そんなことは、経営者の意思一つであり、やり方によって、それほどお金もかからず、手間もかかりません。要は、やる気の問題かと。
成功するEOCの道具立て1:統合リスクマネジメントシステムの導入
システムの個別の機能について述べることはしませんが、黒板・ホワイトボードで情報共有し、そこで目標や方針を組むことと比べたら、はるかに効率性が勝ることは言うまでもありません。位置情報、風向・風速、気象予報を含め様々な外部情報も取り込めます。
一番の効率性は、本部で決定した、戦い方の方針や、現場第一線現場に供給すべき全ての資源調達情報が、一瞬にして、確実に転送され、しかも時系列の記録が保存されることです。
重要なポイントがあります。それは意思決定者に対して、多くの情報リソースの中から、その時点で何を提供することが、最善なのかをコーディネイトできる人材がいれば、ほんとうにそのシステムを活用できるようになります。今後はそのようなスペシャリストをどのように育成し、どのように処遇するかが防災上の大切な観点になると思われます。
成功するEOCの道具立て2:標準行動指針の策定・導入
3.11の時、防災の専門家といわれる方々も、ほんとうは、「何をして良いかわからなかった」とか「作成していたマニュアルが機能しなかった」との感想を漏らしています。
この講座をお読みいただいている皆さまは、想定外の甚大災害時でも、まずはサイズアップから始めることはご理解いただいているはずです。このようにどのような災害が起ころうとも(オールハザード対応)、やるべきこと、議論すべきテーマと、その際に出席すべき人、会議の成果物等のプロトコル(会議体と、その内容、出席者)を決めておけば、災害時に「なすすべもない」というような状況にはなりません。
また、標準行動指針に基づいて、すべての帳票類が、システム的に配送されることにもなります。
「災害対策本部はいつ立ち上げるの?」「誰が出席するの?」というような質問も、その会社の実情に応じて、標準行動指針に盛り込んでおけばよいことになります。
成功するEOCの道具立て3: 本部運営者向けの訓練
繰り返しますが、想定外の甚大災害における問題の本質は、現場第一線に立つ人たちの意欲不足でもなく、知識の不足でもなく、技術不足でもありません。管理の問題なのです。
実際の話ですが、想定災害訓練で、本社の指定された会議室にしかるべき人たちが集まることになりました。実際に集まってみたら、最初の会議内容は、
- 何分で集まれたか
- 社員の安否確認状況はどうか
- 所管官庁、自治体、警察、消防の通報は完了済みか
- 食料等備品は何日分確保されているか
- 本日の宿泊先の手配はどうか
上記のようなことに対して、上級役員までお集まりになられて話題になっていました。
これは特別な例ではありません。このブログの読者の皆さんの会社でも起きているかもしれません。
読者の皆さんはもうお分かりになっている通り、初動でまずやることは上記ではありません。上記はサイズアップの一部ですが、対策本部で話し合うことではなく、冒頭、担当主任がしかるべき人に報告すればよいだけのことです。
全員が集まる必要もないし、全員が集まるのは、サイズアップ情報がある程度入ってきてからでもよいのかもしれません。
問題の本質は、災害対策本部に集まる管理者を中心とする人々のリテラシーなのです。危機管理に対する考え方、発災後のリーダーとしての心構え、標準行動指針に基づいて確実に行うべきことへの正しい認識です。前にも書きましたが、管理者による指揮命令系統の一本化原則やスパンオブコントロール原則に関する認識不足により、災害対応全体の非効率や機能不全を起こしている現実がよく見られます。成功への第三のカギは、災害対策本部で中心的な役割をされる管理者、経営層の方々への教育なのです。
文責: 志村邦彦
ご質問・お問合せ:shimura©jerd.co.jp (©を@マークに変えて送信ください)
日本一わかりやすいインシデント・コマンド・システムのコラム一覧
【第1回】インシデントコマンドシステムの概要・インシデントとは何か?
【第4回】インシデントが起きたら初めにやること①:まずは指揮者(Incident Commander)を決めよ
【第5回】インシデントが起きたら初めにやること②:被害状況を把握せよ
【第6回】インシデントが起きたら初めにやること③:「何はともあれ人命優先」が危機対応の最大原則
【第7回】インシデントが起きたら初めにやること④:メンバーのチェックイン、チェックアウト
【第14回】インシデント・コマンド・システムにおける目標設定
【第15回】計画(IAP:インシデントアクションプラン)を立てる
【第16回】事態対処部門(Operations Section)の役割・組織編成のやり方
インシデント・コマンド・システムのセミナー情報
インシデント・コマンド・システムに関するセミナー情報はこちらをご覧ください。