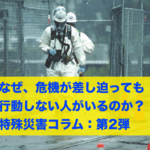ICS(インシデントコマンドシステム)は、現場指揮者(インシデントコマンダー)の指揮のもと災害対応にあたります。
とはいうものの、たった一人の現場指揮者が、すべてのメンバーに対して直接指揮命令を下すには無理があります。一人ひとりからの報告を受けるのも同様に無理のあることです。東日本大震災に匹敵する大規模な災害の場合にはなおさらです。
「ではどうすればよいのか?」というのが今回のおはなしです。今回は、スパンオブコントロール(直接指示の限界)について学んでいきます。
スパンオブコントロール(直接指示の限界)とはなにか?
スパンオブコントロールは、一人の指揮者が直接命令を下せる人数には限界があることを意味しています。その人数は、せいぜい3〜7人(理想としては5人まで)と言われています。
このあたりは、みなさんが会社などの組織で働いたことのある方ならば、ピンとくるものがあるはずです。皆さんだったら、何人の部下までなら管理できるでしょうか?
職種によって異なりますが、よほど優秀な方だったとしても、どこかに管理数の限界があることはお分かりいただけるのではないでしょうか。
ICSにおいても、考え方は通常の組織づくりと同じです。しかも、災害という切羽詰まった緊張状態の中で、短時間で的確な意思決定を行わなくてはならないのに、何十人もの部下の、一人ひとりの報告を聞いて、一人ひとりに丁寧な説明・指示を行うことなど、現実的ではありませんよね。
ICSの発祥の地であるアメリカでは、こうした過去からの経験則に基づいて、指揮者が直接指揮命令を下せる人数を3〜7人までと決めているのです。
ですから、現場指揮者ひとりでみんなに直接指揮をする必要はありません。現場指揮者の直下にそれぞれの部門長がぶら下がります。その部門長の指揮のもとに、それぞれの要員が動くという形になるのです。
また、部門長の下にも、スパンオブコントロールの範囲で、部下がつくことになります。
組織が拡大するにつれて、管理者が増え、階層が増えたとしても、このスパンオブコントロールの原則は守らなければなりません。
気づいたらスパンオブコントロールを超えていた?!

第8回、第9回では、「インシデントの規模や必要な機能に応じて組織を柔軟に編制する」と説明してきました。必要な時に、必要な機能を弾力的に配備するモジュラー型組織編制についても解説しました。
ここでご注意いただきたいことがあります!
それは、スパンオブコントロールを意識しないと気づかぬうちに一人の部門長に大勢の部下がついてしまうということです。
弊社のICS研修の中で、災害を想定したケーススタディによる組織編制演習を行います。そこでも同じようなことが発生します。災害の内容が深刻化・複雑化するにつれ、必要とされる機能は増えてきます。その都度モジュラー型組織を増やしていくわけですが、はっと気付いた時には、一人の現場指揮者や、一人の部門長の下に8人とか10人の部下がぶら下がるという現象です。
発生する事象に応じて組織を柔軟に追加していくことは全く問題ありませんが、ともすれば、事象の対応に追われて、スパンオブコントロールの意識が薄れてしまうことは、よくあります。特に、現場指揮者と事態対処部門長の部下数によく起こります。
研修であれば、笑い話で済むかもしれませんが、現実の災害対応でそのようなことが発生すると、その部分で災害対応の効率性や安全性を大きく損なうことも懸念されます。災害対応の組織編制においては、どうぞスパンオブコントロールをお忘れなきようお願いしますね。
文責: 志村邦彦
ご質問・お問合せ:shimura©jerd.co.jp (©を@マークに変えて送信ください)
日本一わかりやすいインシデント・コマンド・システムのコラム一覧
【第1回】インシデントコマンドシステムの概要・インシデントとは何か?
【第4回】インシデントが起きたら初めにやること①:まずは指揮者(Incident Commander)を決めよ
【第5回】インシデントが起きたら初めにやること②:被害状況を把握せよ
【第6回】インシデントが起きたら初めにやること③:「何はともあれ人命優先」が危機対応の最大原則
【第7回】インシデントが起きたら初めにやること④:メンバーのチェックイン、チェックアウト
【第14回】インシデント・コマンド・システムにおける目標設定
【第15回】計画(IAP:インシデントアクションプラン)を立てる
【第16回】事態対処部門(Operations Section)の役割・組織編成のやり方
インシデント・コマンド・システムのセミナー情報
インシデント・コマンド・システムに関するセミナー情報はこちらをご覧ください。